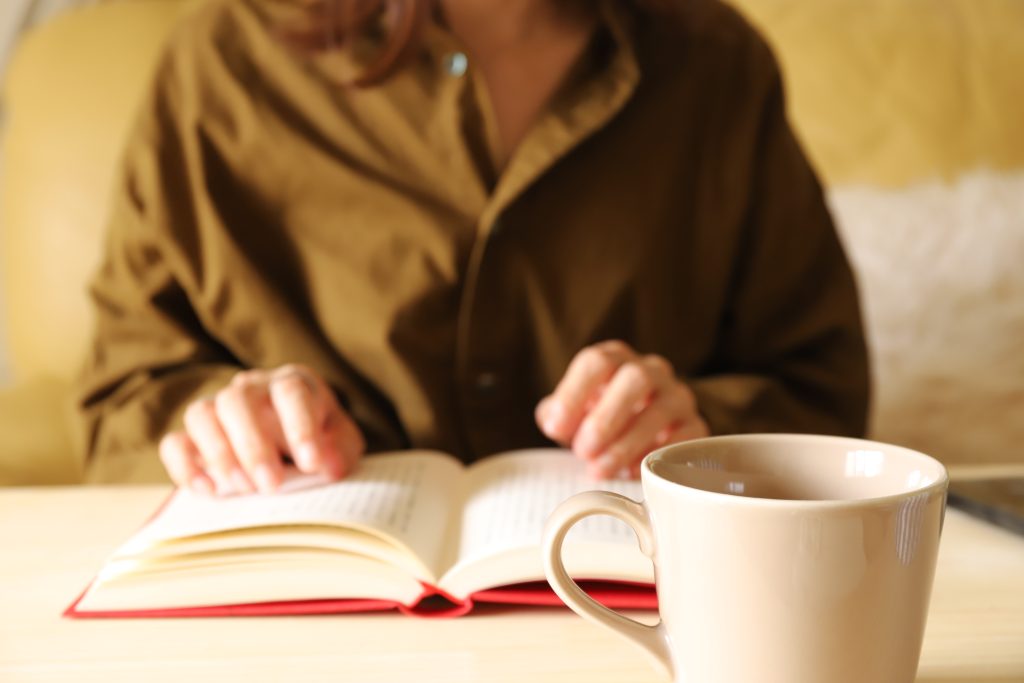「夜眠れない」という中高生は実は少なくありません。そのまま寝ずに登校しようとしても、学校の時間まで起きていられない、明日こそはと思っても今夜も寝られない…など、つらい思いをしていることがあります。
ここではお子さんが自分でも試せる「よく眠るための工夫」を紹介します。
目次
昼夜逆転が起こる背景

昼夜逆転は単なる夜ふかしではなく、体内時計の乱れや生活習慣、運動不足、ストレスなどが影響していることがあります。本人も「眠りたいけど眠れない」と感じている場合が多く、「早く寝なさい!」と叱ってしまうと強いストレスになってしまい、さらに眠れなくなるということもあります。
夕方以降になると体調が回復してくるため、夜を中心に勉強や遊びなどに集中し、そのため夜寝るのが遅くなり、翌朝起きるのが一層辛くなる…という悪循環になっている可能性もあります。
生活リズムを少しずつ整える方法

毎日少しずつ調整する
今日早く寝れば明日は早く起きられる、というわけではありません。一度に完全に朝型に戻そうとせず、就寝・起床時間を少しずつ前倒しするのがポイントです。
例えば就寝時間を毎日15分ずつ早め、朝は同じ時間に起こすという方法もあります。ほかにも夜は照明を少し暗めにし、寝る前のスマホやゲームを控えることで、体に「そろそろ寝る時間だ」と信号を送ることができます。また、昼寝をする場合は20分以内にとどめ、夕食は消化の良い軽めのものを心がけると効果的です。
できそうだな、と思えることから取り入れていくとよいでしょう。
日中の活動・運動を増やす
日中に体を少し疲れさせると、夜の眠りにつながりやすくなります。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を取り入れましょう。ただし、寝る直前の激しい運動は逆効果ですから注意しましょう。
メンタルケアと安心感を提供する
眠れないことを責めてはいけません。「今日は眠れないね」というだけです。お子さんが深刻に受け止め過ぎないように配慮しながら、ゆっくりと過ごせるようにしましょう。
寝る前にリラックスできる環境を整えることも有効です。ぬるめのお風呂につかる、やさしい音楽を流す、照明を落とす、好きな香りをかぐ、ぬいぐるみなど安心できるものをそばに置くなど、安心できる工夫も有効です。
具体的な入眠法の紹介

眠りにつきやすくするために寝る前に行う一連の行動や習慣のことを「入眠儀式」と呼びます。生活を整えるとともに、さらに脳をリラックスモードに切り替える具体的な方法を試してみましょう。中高生でも取り入れやすい方法をご紹介します。
マインドフルネス瞑想
静かに横になり、呼吸に意識を向けていきます。息を吸ったとき「吸っているな」、吐いたとき「吐いているな」と心の中でつぶやきます。雑念が浮かんでも無理に追い払わず、「考えが出てきたな」と気づくだけで大丈夫。5分ほどでも効果があり、心が落ち着いて眠りに入りやすくなります。
認知シャッフル睡眠法
眠る前に頭の中で、関係のない言葉やイメージを次々思い浮かべていく方法です。例えば「りんご」「ミシシッピー河」「最大出力」「オートクチュール」のように、脈絡のない単語をどんどん頭に浮かべていきます。思考の流れをバラバラにすることで、脳がリラックスし、自然と眠りに入る手助けをしてくれます。
米軍式睡眠法
米軍で使われていた入眠法で、どんな環境でも眠れるように考えられています。まず体の力を抜き、顔・肩・腕・脚を順番にリラックスさせます。次に深呼吸をして心も落ち着けます。最後に「何も考えない」「青空に浮かぶ雲を見ている」など平和なイメージを思い描くと、2分以内に眠れるとされています。
4-7-8呼吸法
呼吸のリズムで心身を落ち着ける方法です。横になり、口を閉じて、鼻から4秒かけて息を吸います「1.2.3.4」。そのまま7秒息を止め「1.2.・・・7」、次に8秒かけて口から息を吐きます「1.2….8」。このリズムを4回ほど繰り返すと副交感神経が優位になり、体がリラックスして眠りにつきやすくなります。
必要に応じて専門家に相談
夜眠れないのは、起立性調節障害や睡眠障害の可能性もあるため、必要に応じて医師や学校に相談することも大切です。家庭でのサポートと医療の両輪で改善を目指しましょう。
まとめ

- ・眠れないことを責めない
- ・少しずつ生活リズムを整える
- ・ 運動や日中の活動で体を適度に疲れさせる
- ・ 食事や昼寝、寝る前の環境も工夫する
- ・ 自分に合う入眠儀式を見つける
- ・ 必要に応じて医療や学校と連携する
 通信制高校を検討されている中高生とその保護者の方にお役に立てるよう、通信制高校や大学受験に関する情報を発信していきます。
通信制高校を検討されている中高生とその保護者の方にお役に立てるよう、通信制高校や大学受験に関する情報を発信していきます。だれでも才能を持っています。でもその才能は優れた学習システムと優秀かつ熱心な先生との出会いなしに開花することはできません。「英語が苦手」「数学が苦手」という人は、教え上手な先生に出会ってこなかっただけ。正しいやり方で学びの楽しさを味わうことができれば、「英語が好き」「数学が好き」に変身します。
「だれでも才能を持っている」という理念のもと、あなたに「やればできる」「学ぶことは楽しい」という体験をさせる、これが私たちの使命です。