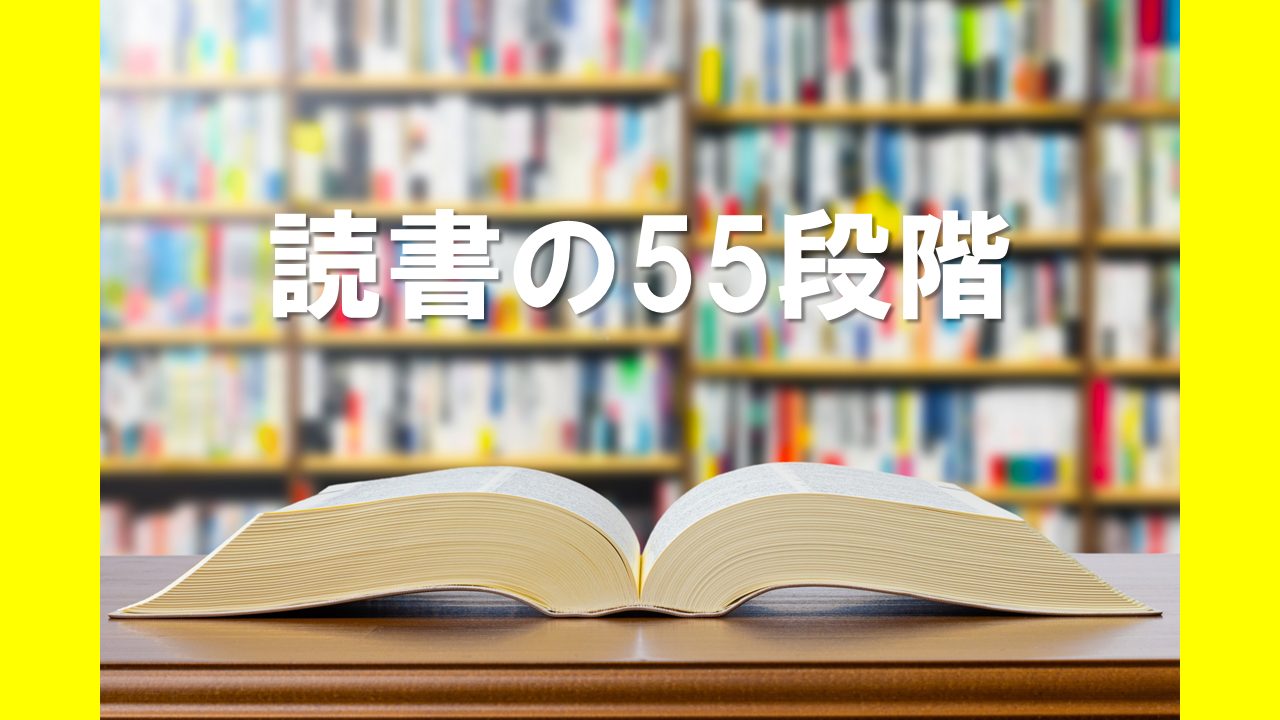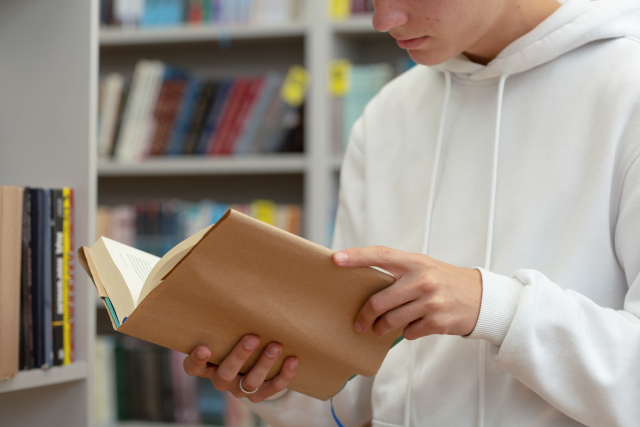
人生は限られた時間とお金の中で過ごすもの。
だからこそ、読書を通して効率よくさまざまな経験を疑似体験することが大切です。読書から得た知識や考える力は、あなたの人生をより豊かにしてくれます。
目次
読書は自分を成長させる最高のツール
読書は、本との出会いを通して多くの知恵や価値観に触れることで、自分自身の可能性に気づくことができます。
そして、読書は新しいアイデアの宝庫です。自分の世界を広げるのにもって来いと言えるでしょう。
「なりたい自分」を実現した人たちの共通点は?
世界的なスポーツ選手や音楽家、今を時めく起業家などなど、なりたい自分を実現してきた人たちのインタビュー記事や自伝などの読んでみると、共通点を見つけることができるかと思います。それは「読書が好き」ということです。
「なりたい自分」を実現して社会で活躍している方たちの多くは、読書を通じて、社会で役立つたくさんの知恵を自然と身につけています。だから自信を持って未来に進めるのかもしれませんね。
「あの人、どんな本読んでいるのかな?」とちょっと気になりませんか?
ビル・ゲイツ氏
小学生の頃から筋金入りの読書好きで、小説、SF、果てには百科事典まで、夢中になって読んでいたという逸話もあるほどです。「食事中は本を読むな」と叱られたということですから、食べながら読んでたんですね…
菅田将暉さん
俳優の菅田将暉さんは、年間100冊以上の本を読むことで知られています。無類のマンガ好きとしても有名です。きっかけは星新一さんの本。読書を通じて新しい視点や感性を磨き、演技の幅を広げています。
常田大希さん
人気バンド「King Gnu」の常田大希さんは、音楽制作のヒントを得るために年間80冊以上の本を読むとのこと。多様なジャンルの本から刺激を受けて、独自の世界観を広げています。
中条あやみさん
モデルで女優の中条あやみさんは、ファッションや哲学に関する本が好きで、知的好奇心を大切にしています。読書を通じて内面からの美しさも磨いているそうです。特に『星の王子様』がお気に入りだとか。
読書は身近な楽しみ
読書を通じて効率よく多くの知恵を身につけることができますが、しかしそれだけではありません。読書は「楽しみ」でもあります。
学校の先生や保護者の方からは「子どもに本を読ませたいけれど、なかなか…」という声が聞こえてきます。確かに今はゲームや映像など、色々なコンテンツがありますから、わざわざ「本」を読ませるというのは難しい側面があるのかもしれません。その一方で、デジタルの普及により、今まで以上に手軽に読書を楽しむことが可能になったのも事実。スマホやタブレットでマンガを読む、小説を読む、というのも一般的になってきました。

読書は自分を成長させる最高のツール
多くの中学生・高校生は、読書を食わず嫌いしています。「読書は苦手」とか「読書感想文って大っ嫌い」という声は珍しくありません。しかし、これは「まだ、いい本に出合えていないから」です。「いい本」というのは何も世界の名著とか不朽の名作と言われるものではありません。あなたの心が動く、あなたの今に影響を与えるような本のことです。きっとこれから出会いがあります。
読書を“苦手”から“好き”に変える『読書の55段階』
四谷学院と言えば「55段階」ではないでしょうか?
実は四谷学院高等学校(通信制高校)では、「読書の55段階」という独自の学習法があります。
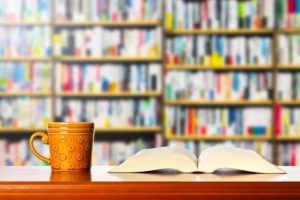
色々な栄養をバランスよくとらないと成長が偏ってしまうのと同じように、スポーツや勉強、ゲーム、ダンス、コミュニケーションやパソコンなど、あなたの成長のためには色々なものがしかるべきタイミングで必要になってきます。
四谷学院高校の皆さんには、そんなときに強い味方「読書の55段階」です。おすすめの本リストがあるので、これまで読書習慣がなかった人でも無理なく楽しみながら読書が好きになれますよ✨
読書の55段階について詳しくはこちら
2025年4月に開校した通信制高校、四谷高等学校(茨城県筑西市折本895)は「だれでも楽しみながら読書が好きになる 読書の55段階」のカリキュラム紹介ページを公開しました。 ▼四谷学院高等学校 読書の55段階 https …
最後に

今は、新しく本を買わなくても、スマホさえあれば本を読める時代になっています。せっかくですから、読書の楽しみも知ってほしいと思います。
ぜひ高校生になったら、あなたの世界を作るものとして「読書」を仲間に入れてくださいね。
 通信制高校を検討されている中高生とその保護者の方にお役に立てるよう、通信制高校や大学受験に関する情報を発信していきます。
通信制高校を検討されている中高生とその保護者の方にお役に立てるよう、通信制高校や大学受験に関する情報を発信していきます。だれでも才能を持っています。でもその才能は優れた学習システムと優秀かつ熱心な先生との出会いなしに開花することはできません。「英語が苦手」「数学が苦手」という人は、教え上手な先生に出会ってこなかっただけ。正しいやり方で学びの楽しさを味わうことができれば、「英語が好き」「数学が好き」に変身します。
「だれでも才能を持っている」という理念のもと、あなたに「やればできる」「学ぶことは楽しい」という体験をさせる、これが私たちの使命です。