
こんにちは、四谷学院の田中です。
通信制高校を検討している方の中には、「校則がゆるいって本当?」「自由に過ごせるの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。確かに髪染めやピアス、メイク、ネイル、制服など、高校の規則がどれほどなのか気になる部分です。
この記事では通信制高校の校則の実態について、全日制高校との比較や具体的な事例を交えながら詳しく解説します。
目次
通信制高校の校則は本当にゆるい?
一般的に、通信制高校は全日制高校に比べて校則が緩やかで自由度が高いとされています。しかし、すべての通信制高校が一律に自由というわけではありません
例えば、制服の着用が義務の学校もあれば、私服通学が可能な学校もあります。髪型や髪色、メイク、アクセサリーの制限についても、学校によって対応はさまざまです。
通信制高校の校則が緩い理由:毎日の授業がないから
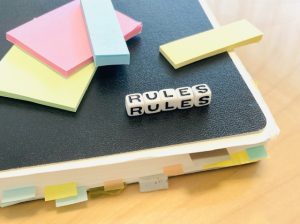
通信制と全日制の学び方の違い
| 項目 | 通信制高校 | 全日制高校 |
|---|---|---|
| 登校頻度 | 月1~週1(学校による) | 週5日登校 |
| 授業形態 | 自宅学習+スクーリング | 教室での一斉授業 |
| 学習管理 | 自己スケジュール管理 | 時間割に従う |
| 先生との関わり | 必要に応じて指導・オンラインや郵送など通信がメイン | 毎日対面 |
つまり、通信制高校では生徒が学校に集まるわけではなく、在宅スタイルがメインであるため、毎日の生活を管理するための厳しい校則の必要性が低くなります。
全日制高校で校則が厳しい理由

全日制高校では、多くの生徒が同じ空間で毎日生活します。そのため、秩序やトラブル防止の観点から、服装や頭髪、アルバイトなどのルールで統一が図られています。
つまり、集団管理の必要性から校則が厳しくなる傾向にある、ということです。
通信制高校で自由が実現している具体例
- 私服登校OK
- 髪型・髪色の自由度が高い
- アルバイトOK、推奨する学校もあり
- メイク・ネイル・ピアスも禁止されていないケースが多い
校則がゆるい=何をしてもいい訳ではない
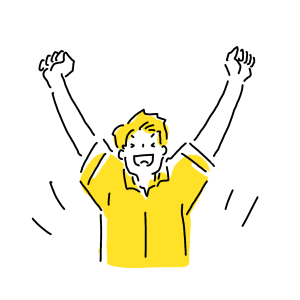
通信制高校では、一律の統制が少ない分、自己管理力が求められます。自由な環境だからこそ、自分で決めて自分で行動する力が大切になります。
- 学習計画を自分で立てる
- 課題提出を自己管理する
- 自分のペースで学習を進める
生徒の自律を支援する通信制高校の仕組み

1. 担任・アドバイザーによる個別支援
学習スケジュールの管理や進捗状況のチェックを行い、生徒のモチベーション維持をサポートします。
2. 定期的な面談・カウンセリング
学習・生活面の不安を取り除き、精神的サポートも提供します。高校によっては専門のカウンセラーが着く場合もあります。
3. 学習管理ツール・アプリ
進捗可視化、リマインダー、チャット相談など、様々なツールやアプリを導入している高校があります。
四谷学院高校では、進学コースには「受験コンサルタント」がつき、そのほかのコースには「ライフコンサルタント」がつきます。個別面談やガイダンス、保護者サポートも充実。保護者向けガイダンスではお子様への声のかけ方や最新の入試情報などもお伝えしており、学校&家庭の両面での支援をサポートいたします。
進学コースの「55段階学習システム」を含む四谷学院の学習システムについては、ホームページでもご確認いただけます。
55段階個別指導とは
よくある質問(Q&A)
- Q1. 通信制高校って髪を染めてもいいの?
- A. 校則で禁止されていない学校が多く、個性を尊重する風潮があります。
- Q2. アルバイトはしても大丈夫?
- A. 学校によって異なります。社会性を育てる目的で推奨されている学校もあります。
- Q3. 自由すぎてサボってしまいそう…
- A. 継続的なサポートや個別支援が充実している通信制高校であれば、安心して学べます。
四谷学院高校は「自由」と「自律」の両立を支援する学校

四谷学院高校は、自由と自立、両方を支援する通信制高校です。
- 個別サポート体制
- 成功への体験プログラム
- 自由な校風+相談しやすい環境
などの仕組みにより、自分のペースで自分の未来を築く力を育てていきます。
🏫 通信制高校を検討しているあなたへ
四谷学院高校では、自由と安心を両立した学びの環境を整えています。ぜひオンライン学校説明会にご参加ください。個別相談会も実施中です!
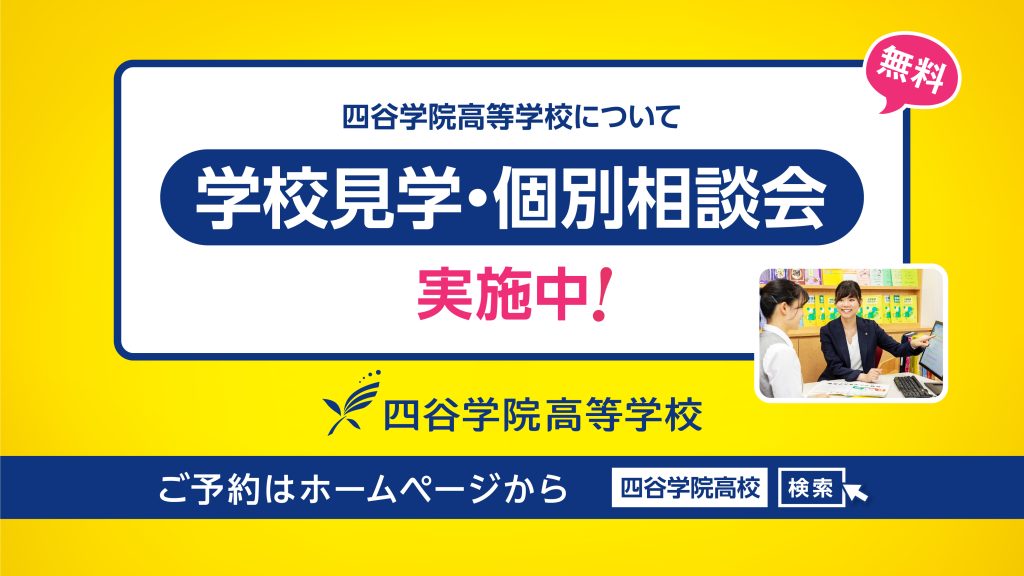
 通信制高校を検討されている中高生とその保護者の方にお役に立てるよう、通信制高校や大学受験に関する情報を発信していきます。
通信制高校を検討されている中高生とその保護者の方にお役に立てるよう、通信制高校や大学受験に関する情報を発信していきます。だれでも才能を持っています。でもその才能は優れた学習システムと優秀かつ熱心な先生との出会いなしに開花することはできません。「英語が苦手」「数学が苦手」という人は、教え上手な先生に出会ってこなかっただけ。正しいやり方で学びの楽しさを味わうことができれば、「英語が好き」「数学が好き」に変身します。
「だれでも才能を持っている」という理念のもと、あなたに「やればできる」「学ぶことは楽しい」という体験をさせる、これが私たちの使命です。







